
常滑窯の誕生
常滑窯は、猿投窯を母として平安時代末期に誕生しました。六古窯の中では一番古く、最大の生産量を誇りました。その最大の消費地が奥州平泉(現・岩手県平泉町)です。そこから出土する壺の大半は、常滑焼の「三筋壺(さんきんこ)」です。その用途は、経文を壺に入れて埋蔵するために使われた可能性が高いといわれています。写真の「常滑三筋壺」は、常滑窯の初期のもので、自然釉が口縁から肩に降りかかり、白く変色して黒褐色と茶褐色の斑(まだら)に焼き上がっています。口縁は鍔口(つばぐち)状に外に折れて開き、胴には太い二重沈線の三筋文が施されています。三筋文壺は、金属性の仏具の意匠を祖型とするといわれています。三筋によって胴を4つに分け、これに口を加えて、密教の空・風・火・水・地の五輪思想を表わすといわれています。
平安時代末期、平泉を拠点とし、東北一帯を支配した奥州藤原氏は、豊富に産出した砂金や北方交易を背景に繁栄を極めました。その約百年間に、中尊寺金色堂を築き、毛越寺(もうつうじ)や宇治の平等院を模した無量光院(むりょうこういん)を造営しました。藤原四代が築いた寺院や遺跡が、後の鎌倉幕府の街づくりや文化に大きな影響を与えたといいます。それは、これまでの京都を中心とした文化に対して、新しい文化が地方で始まったことを意味します。12世紀初めに渥美窯(あつみよう)の工人によって平泉に「花立窯(はなだてよう)」が築かれ、大碗・碗・片口鉢・甕(かめ)などが生産されました。しかし、この試みは焼成に失敗し、成功しなかったようです。この渥美窯も常滑窯と同じく、猿投窯を母として平安時代末期に誕生しました。

六古窯の父と呼ばれた「常滑窯」
常滑は知多半島の中ほどにあり、伊勢湾に面しているため海運に恵まれていました。常滑焼は、その海上交通を利用して北は津軽半島の十三湊から南は種子島まで運ばれています。12世紀末から13世紀初期になると福井県丹生郡越前町に常滑窯の技術の影響を受けた越前窯が開窯します。13世紀中葉になると、兵庫県篠山市今田町に丹波窯が開かれ、続いて滋賀県甲賀市信楽町に信楽窯が誕生します。常滑窯が六古窯の父と呼ばれる理由は、こうした事情からです。越前窯や丹波窯、信楽窯も常滑窯の技術の影響を受けますが、水や土壌が変われば野菜の味も異なるように、やきものの特徴も変わります。六古窯には、その地方の風土性、地域性が内包され、それぞれの展開が見られるといってもいいでしょう。
常滑焼の研究に生涯をささげた沢田由治氏
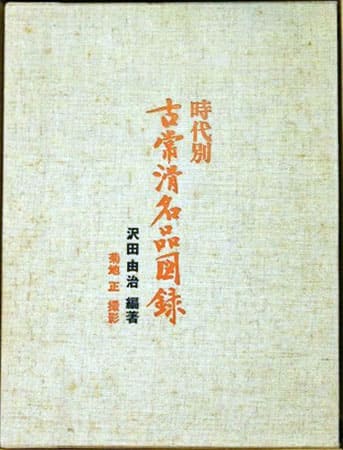
その常滑焼の研究に生涯をささげたのが、沢田由治(よしはる)氏(1909~1994)です。沢田氏は、戦中・戦後と常滑市内の製陶所に土を供給する日本酸器工業有限会社を取り仕切り、常滑の陶業界に尽力されました。1952(昭和27)年、陶磁学者・小山冨士夫氏の講演「日本陶磁史における古常滑焼」を聞き、日本の陶磁史を明らかにする上で常滑焼の研究が欠かせないことを痛感し、小山氏の指導の下で「常滑古窯調査会」を発足。知多半島に点在する古窯の分布調査と発掘調査を行いました。また、1961(昭和36)年には伊奈製陶(現LIXIL)の援助をもらい常滑市立陶芸研究所の開設に尽力、のちに所長、顧問を歴任しました。「常滑焼流通の背景には天台の経塚思想がある」というのが沢田さんの持論です。それは、古常滑の壺が経巻埋納容器や蔵骨器として経塚や墳墓(ふんぼ)から出土する多くの例を根拠としたものですが、13世紀中ごろには消滅します。古常滑の三筋壺や水瓶(すいびょう)に崇高な信仰心が秘められているのは、そうした理由からでしょう。沢田さんの古常滑研究の業績は、1974(昭和49)年刊行の『時代別古常滑名品図録』に代表されますが、他にも多くの著述を手掛けています。相手がどんな地位にある人でも、少しも物おじせず自分の主張をズバリというところから、「常滑の大久保彦左衛門」と呼ばれていました。
常滑窯の「紐輪積み」成形技法
中世の街づくりにとって、壺・甕・すり鉢の三種器は必要欠かせざるものでした。常滑の鉄分の多いザックリとした土は、低い温度でもよく焼き締まるため、壺・甕・すり鉢の生産には適していたのでしょう。この三種の成形は「紐輪積(ひもわづ)み」成形といって、紐状の粘土を輪状にして積み上げていく技法で、縄文時代から行われていた成形です。常滑焼ではこの紐輪積みの繋ぎ目を密着させるため、木彫りの押印で表面を押さえたものがあります。写真の「三耳壺(さんじこ)」がその例です。赤褐色の器肌に、口頸(こうけい)部から腰部にかけて白い灰を被り、さらに淡緑色の自然釉が大きく流れて、先端部分に数筋の玉垂れが見えます。張り出した肩には3カ所に耳が付き、耳と耳の間に刻印が横列に押されています。

常滑窯の魅力
小さな底部に対して肩が大きく張り出した豪快な常滑大甕の造形は、「紐輪積み」成形技法によって生まれたものですが、そうした造形は、時代によって変化します。常滑窯の大甕や大壺の口縁部の先端を「端作り(はしづくり)」といいます。やや上に向かって外開きとなり、その先端が薄くなってゆくのが平安時代の特徴です。鎌倉時代になると口作りの先端が直角に近く折り曲げられる傾向があります。この折り曲げられた形を指して「折り端(おりは)」と呼びます。また、平安時代のものは比較的薄造りで、肩部に膨らみをもたせ、底部にかけて細くなるのが特徴です。鎌倉時代になると、口縁から肩にかけての膨らみが弱くなり、肩から底部にかけてなだらかな曲線をもって細くなる形態に変化します。
常滑の大甕や大壺を眺めていると、古武士のような力強さと雄渾(ゆうこん)な大らかさを感じます。その雄渾な大らかさこそ、常滑窯の魅力といえましょう。

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[74]1月:母とのささやかな茶会](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/teaparty01-218x150.jpg)
![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[73]12月:冬はやっぱり鍋料理](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/hot-pot-dishes01-218x150.jpg)
![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[72]11月:番外編―ハワイ・マウイ島滞在記](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/hawaii-maui01-218x150.jpg)
![やきもの曼荼羅[3]料理と器 北大路魯山人(其の二)](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/rosanjin-tounoji-100x70.jpg)
![やきもの曼荼羅[35]日本のやきもの17 肥前磁器とその背景](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2022/06/fuyodesometsuke-100x70.jpg)